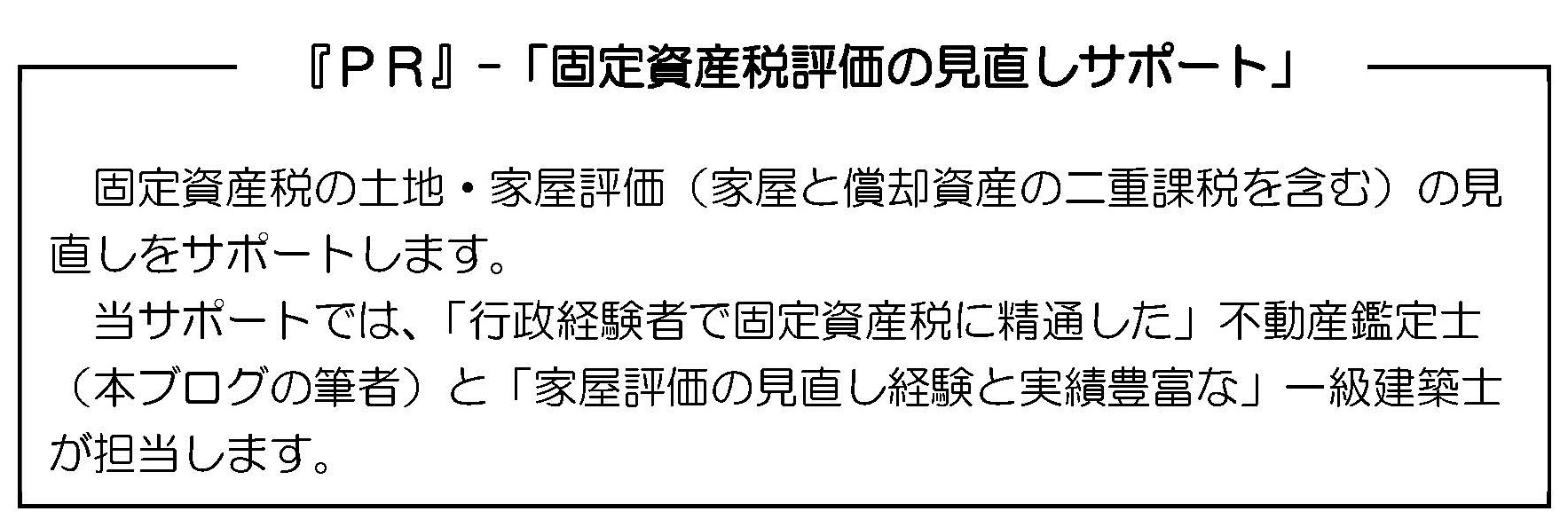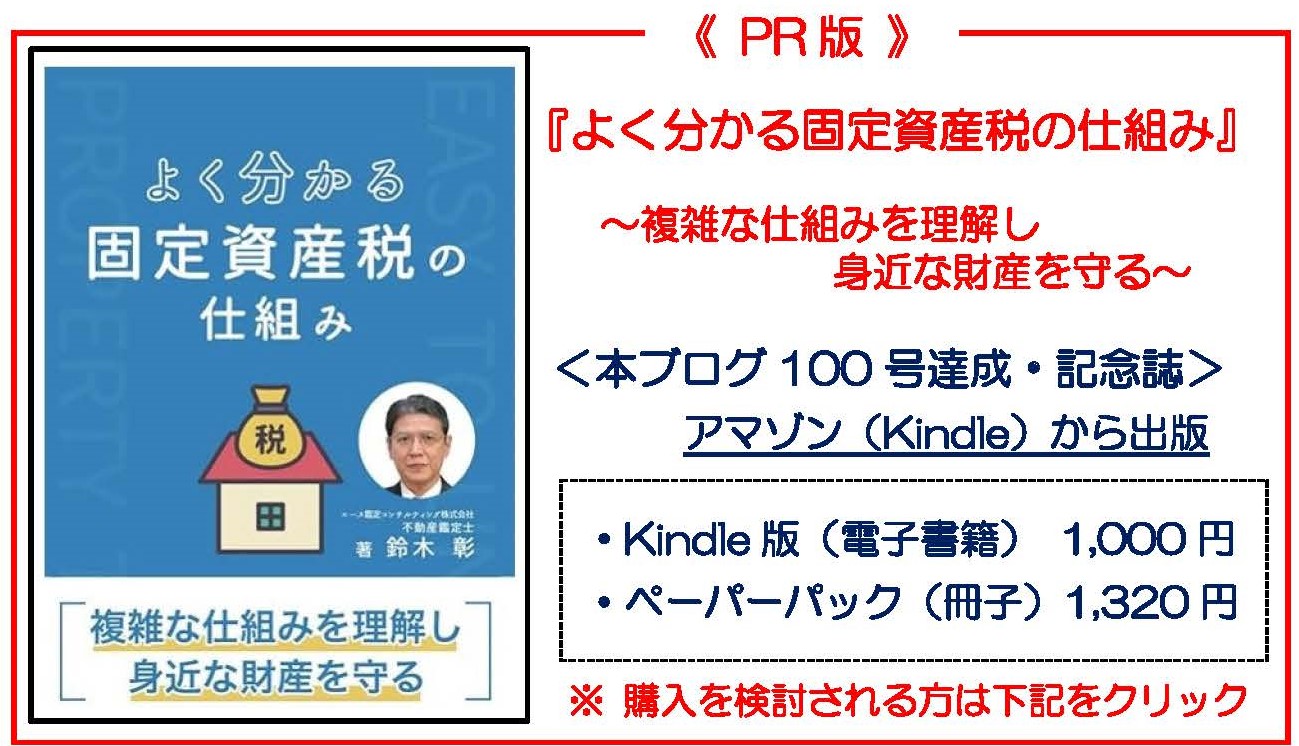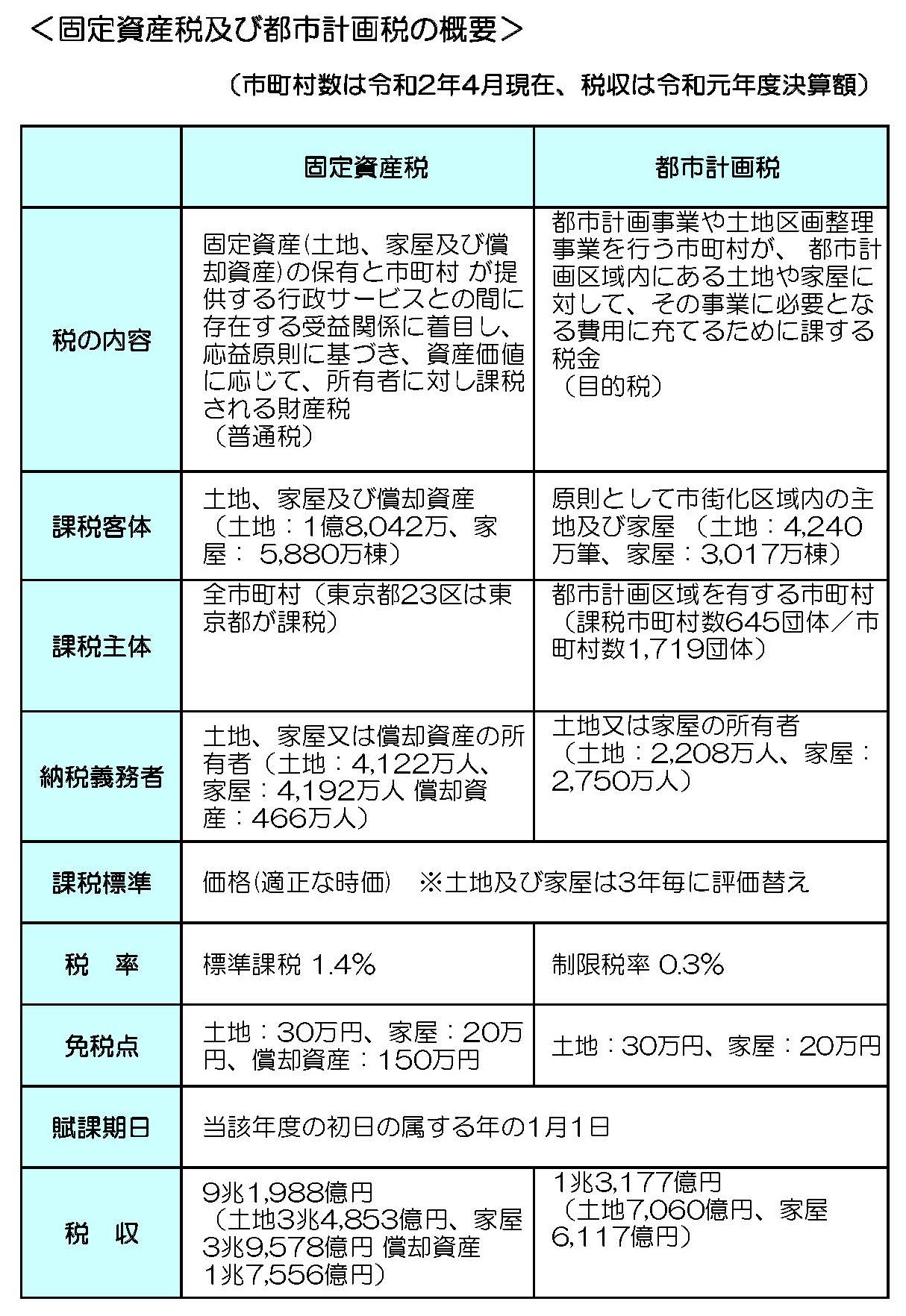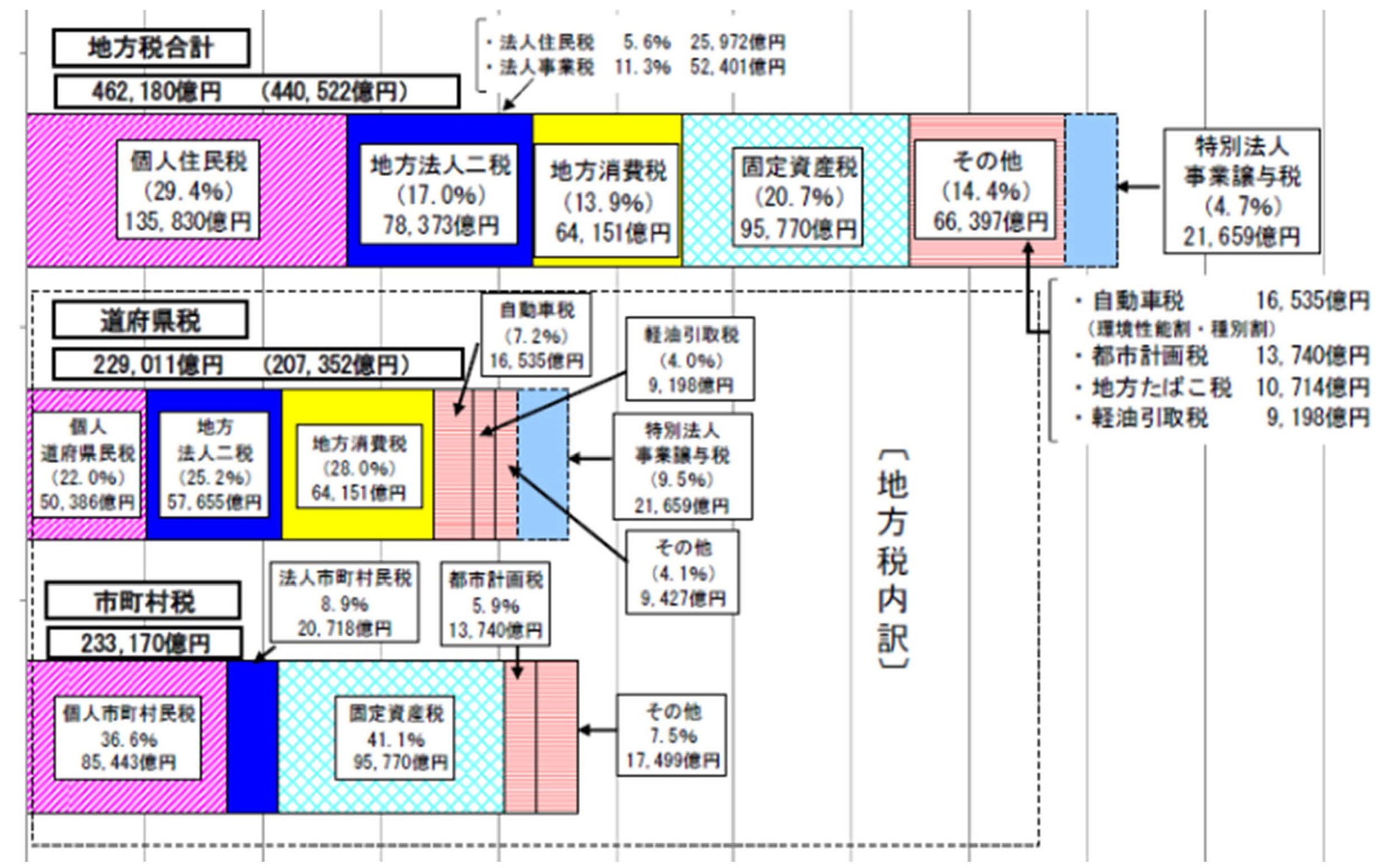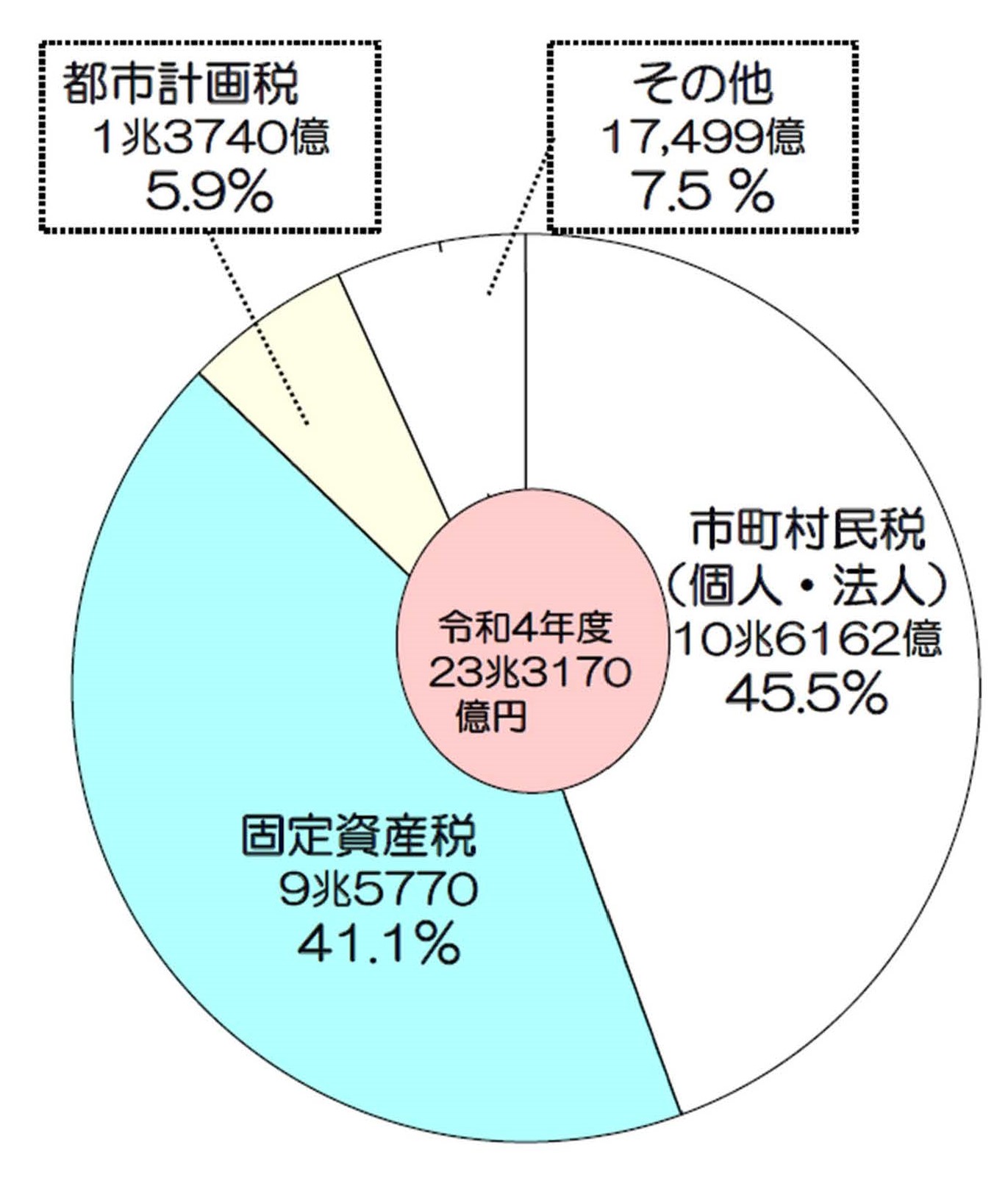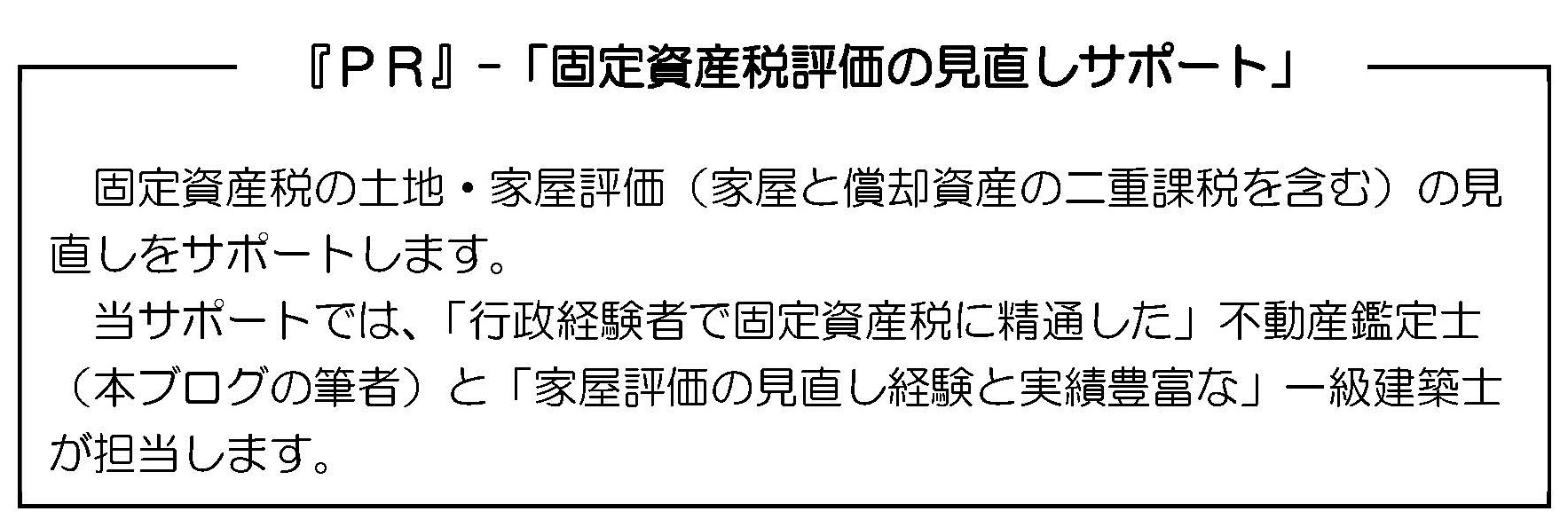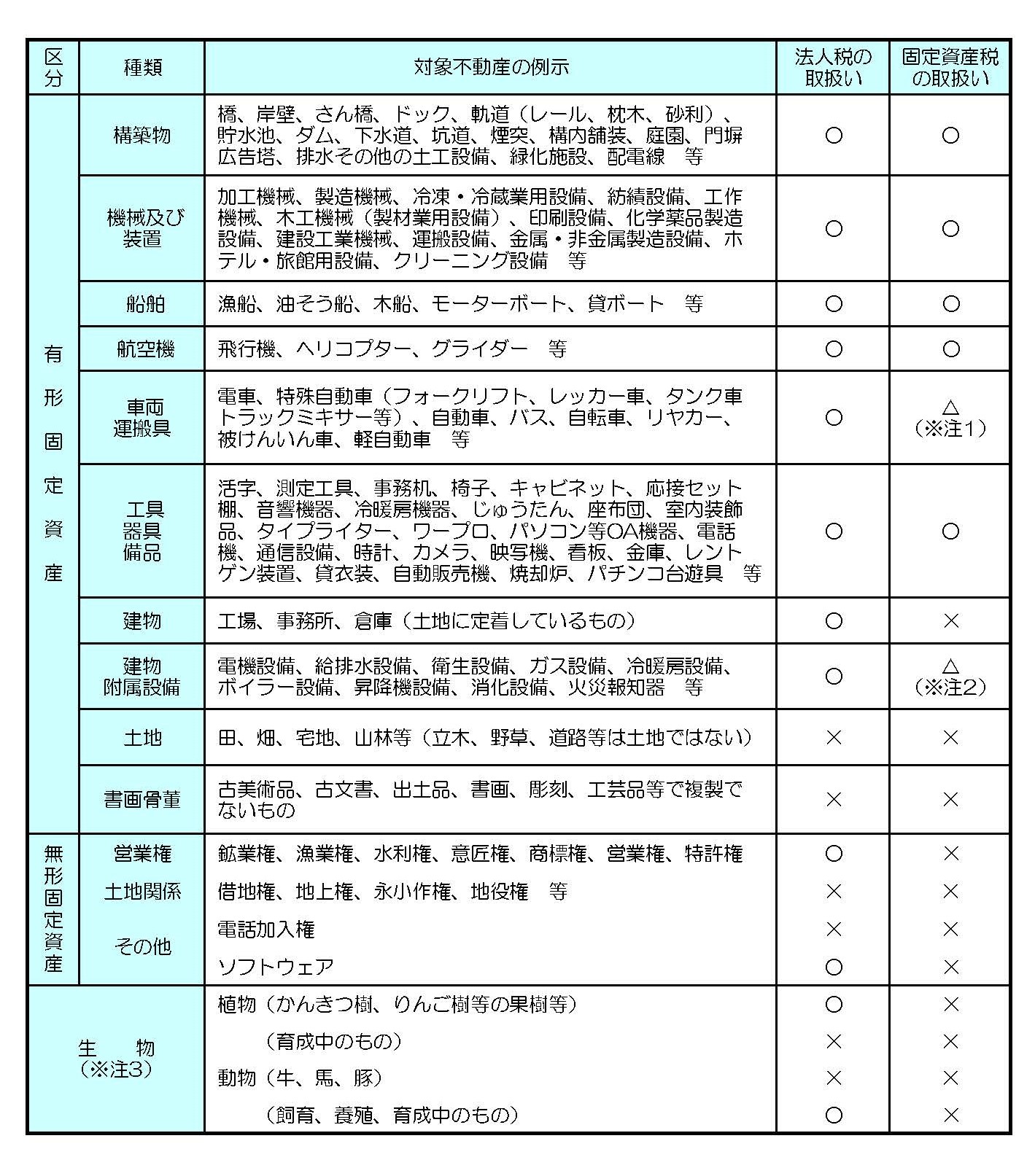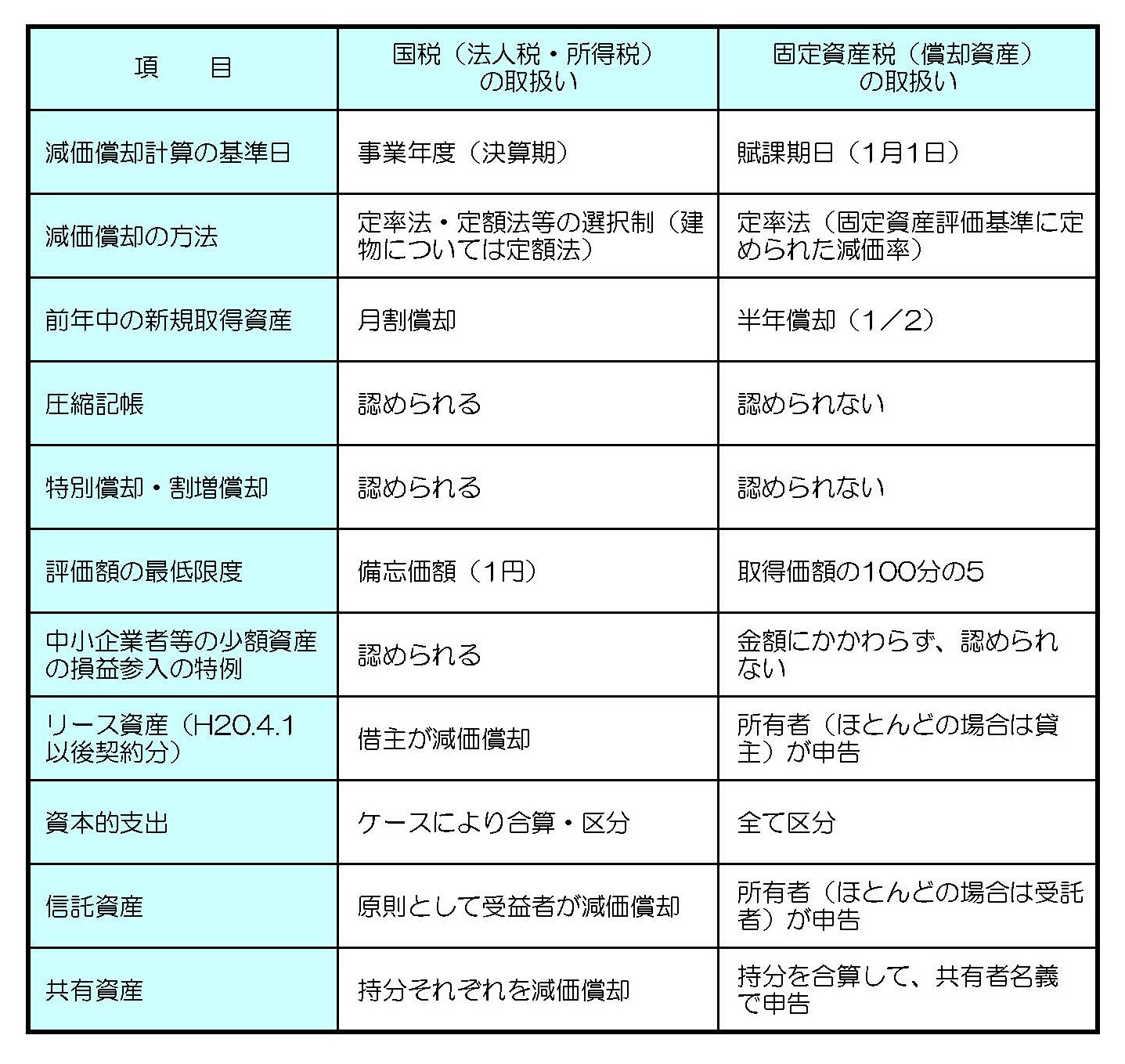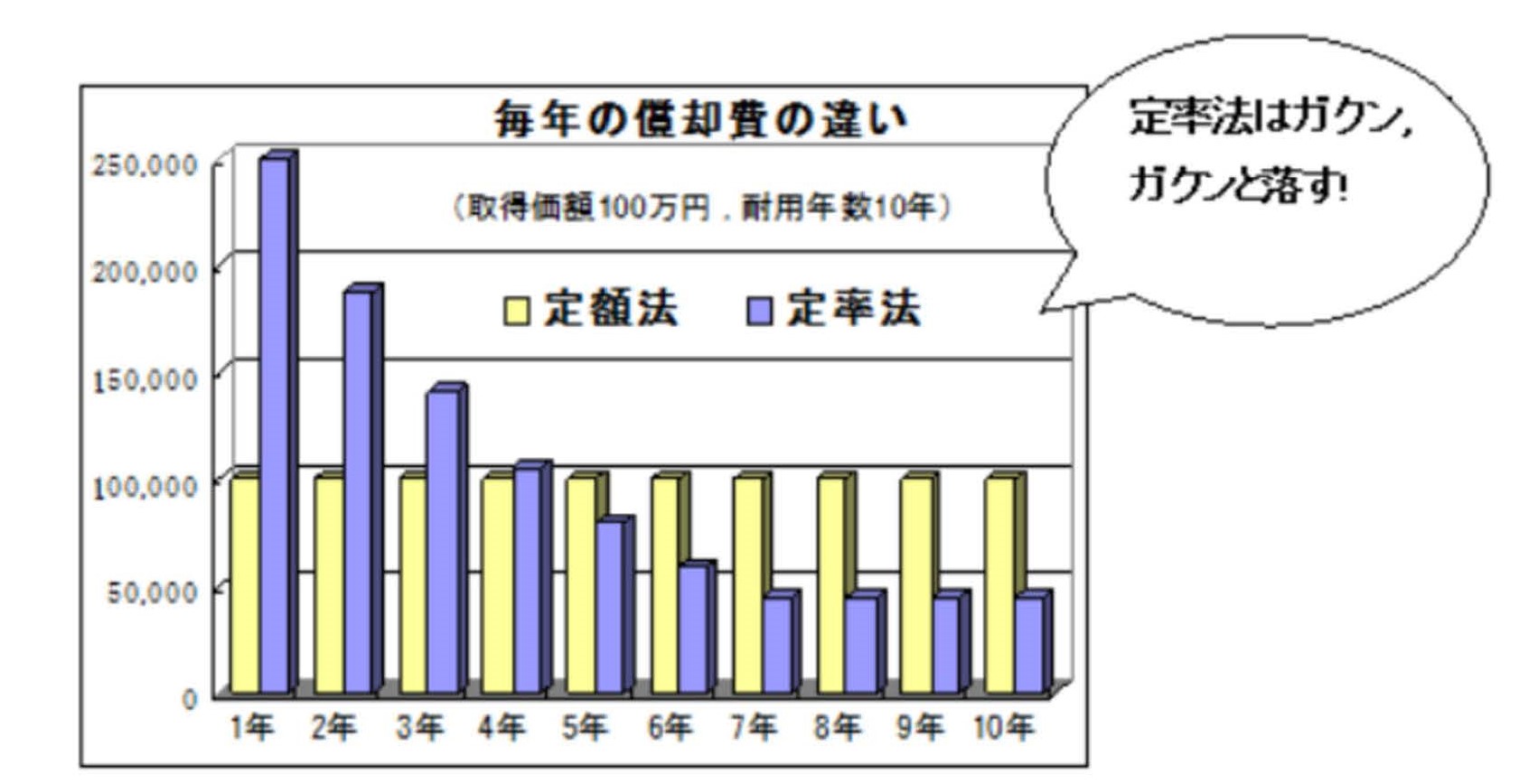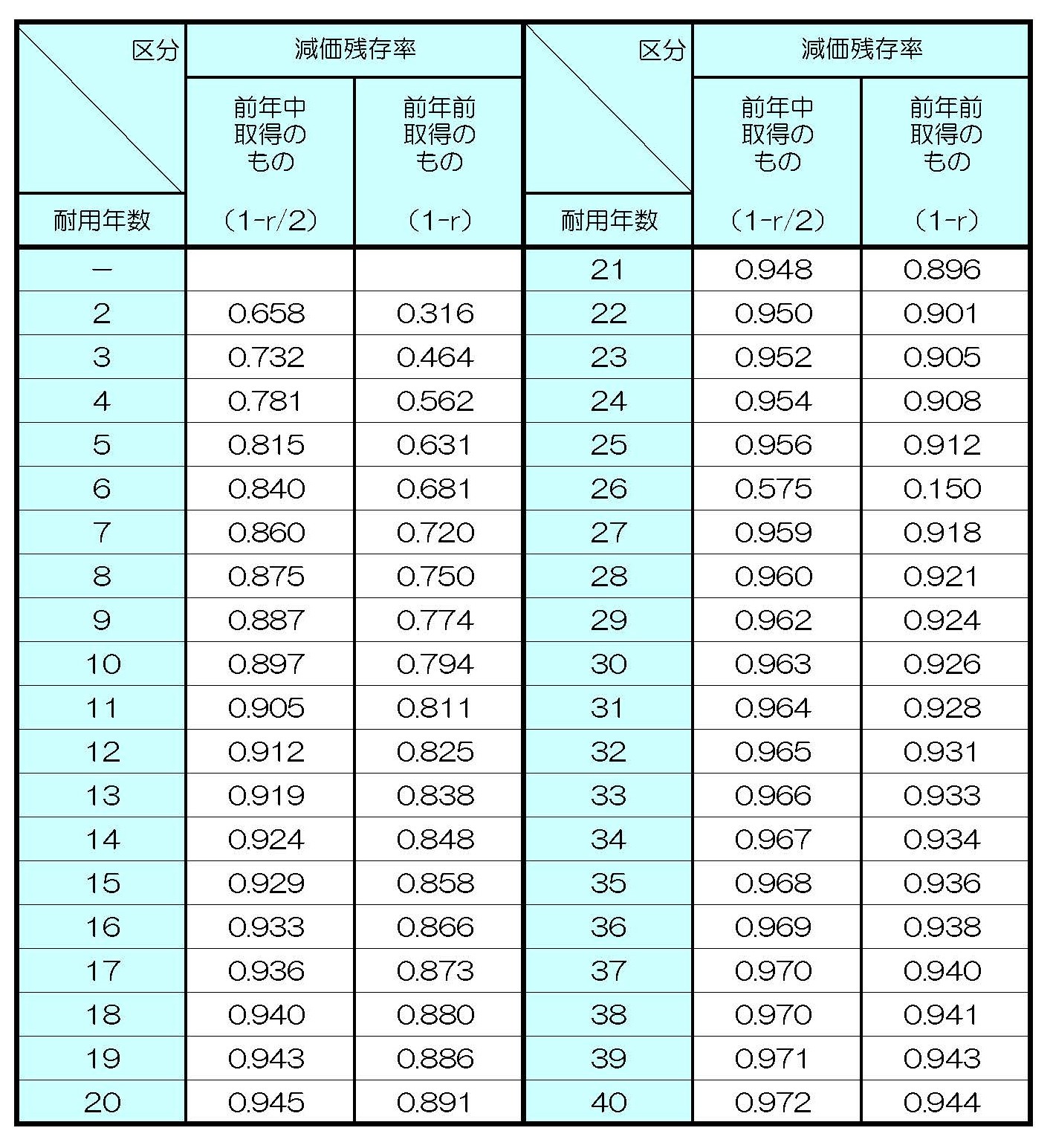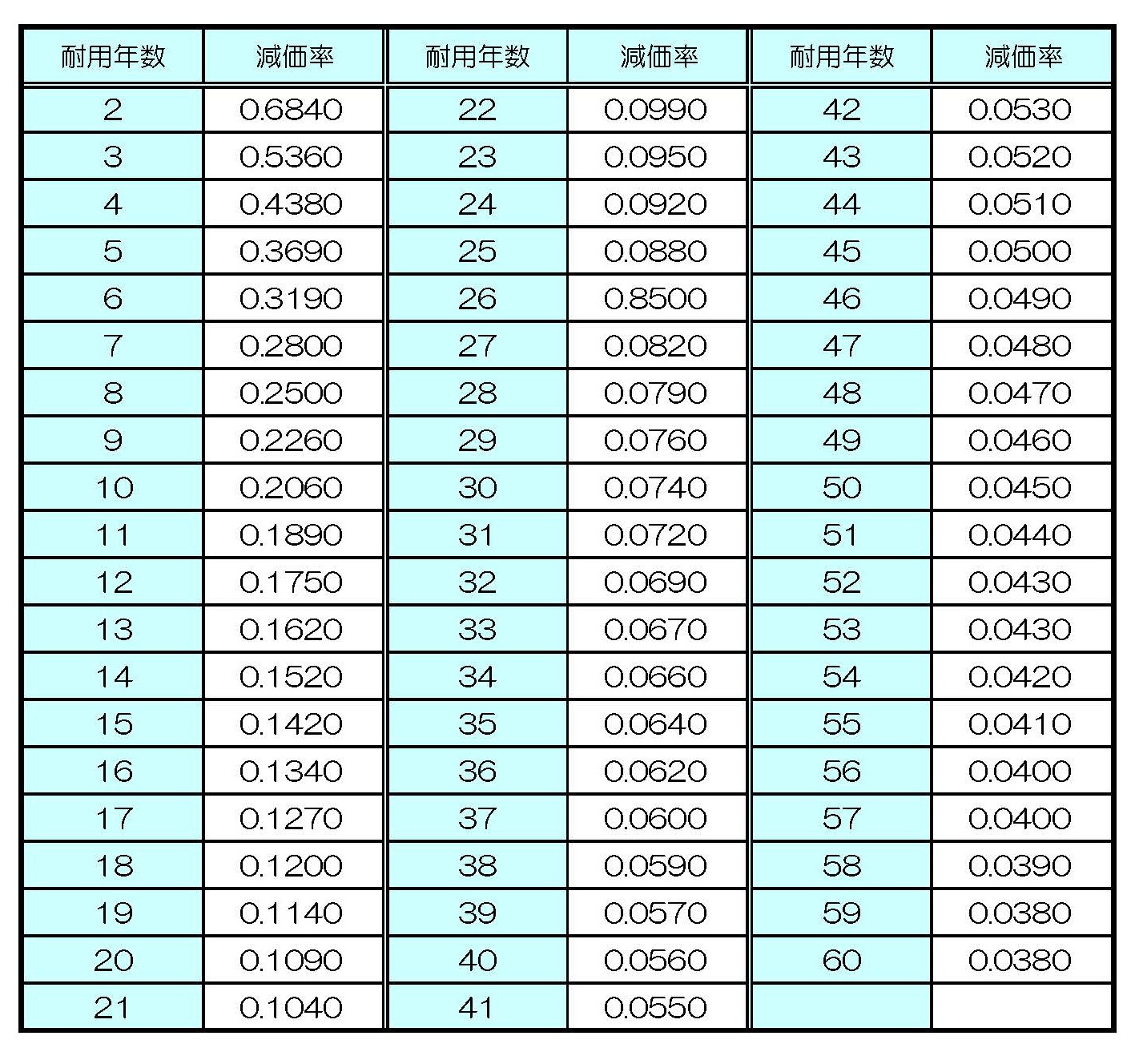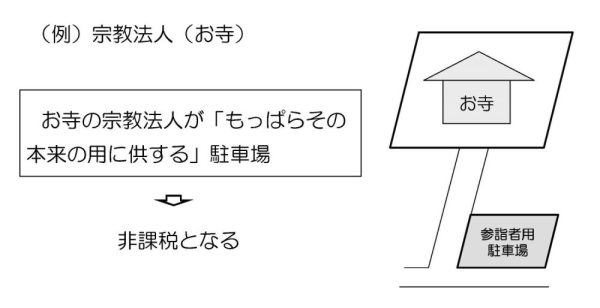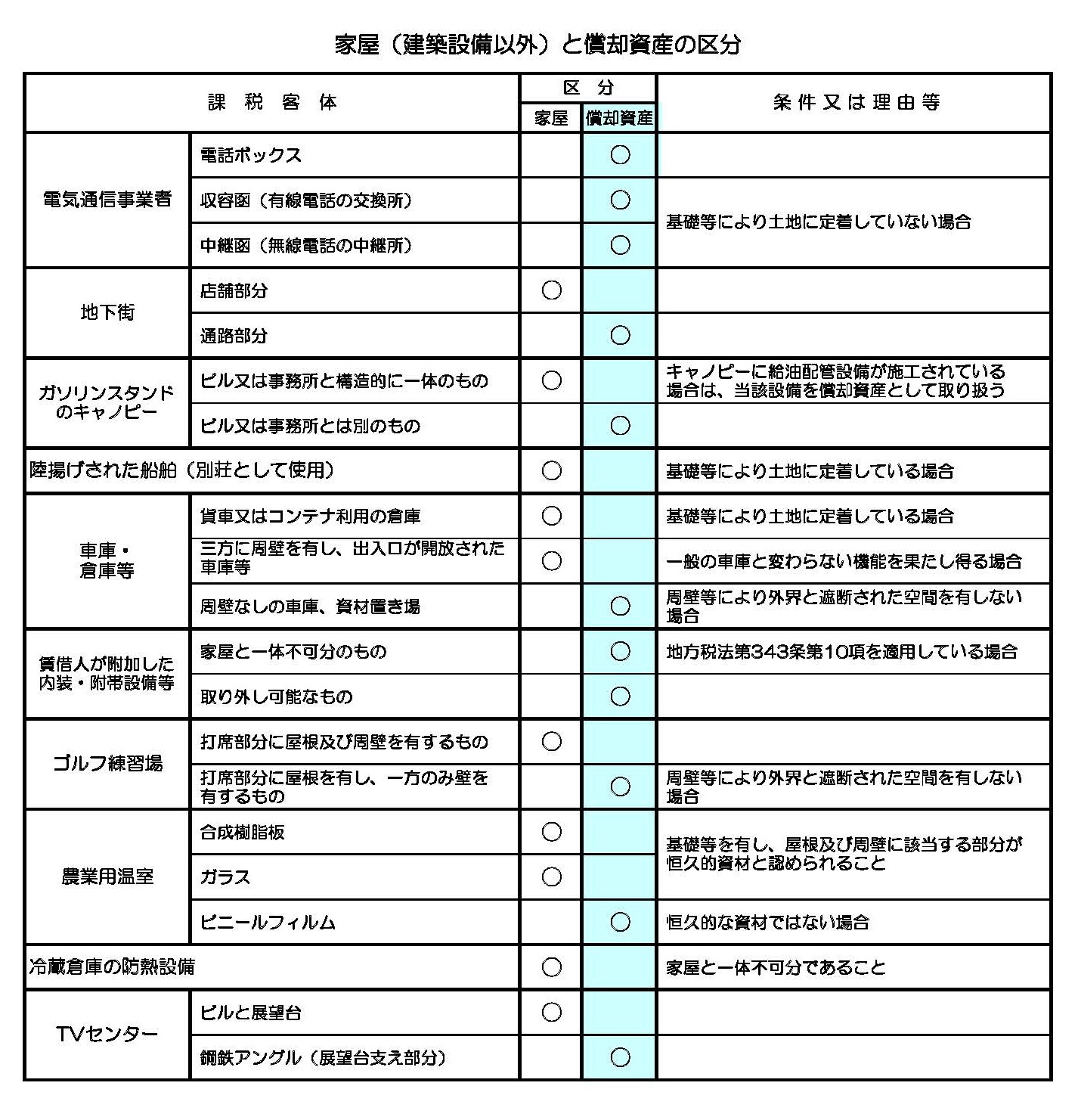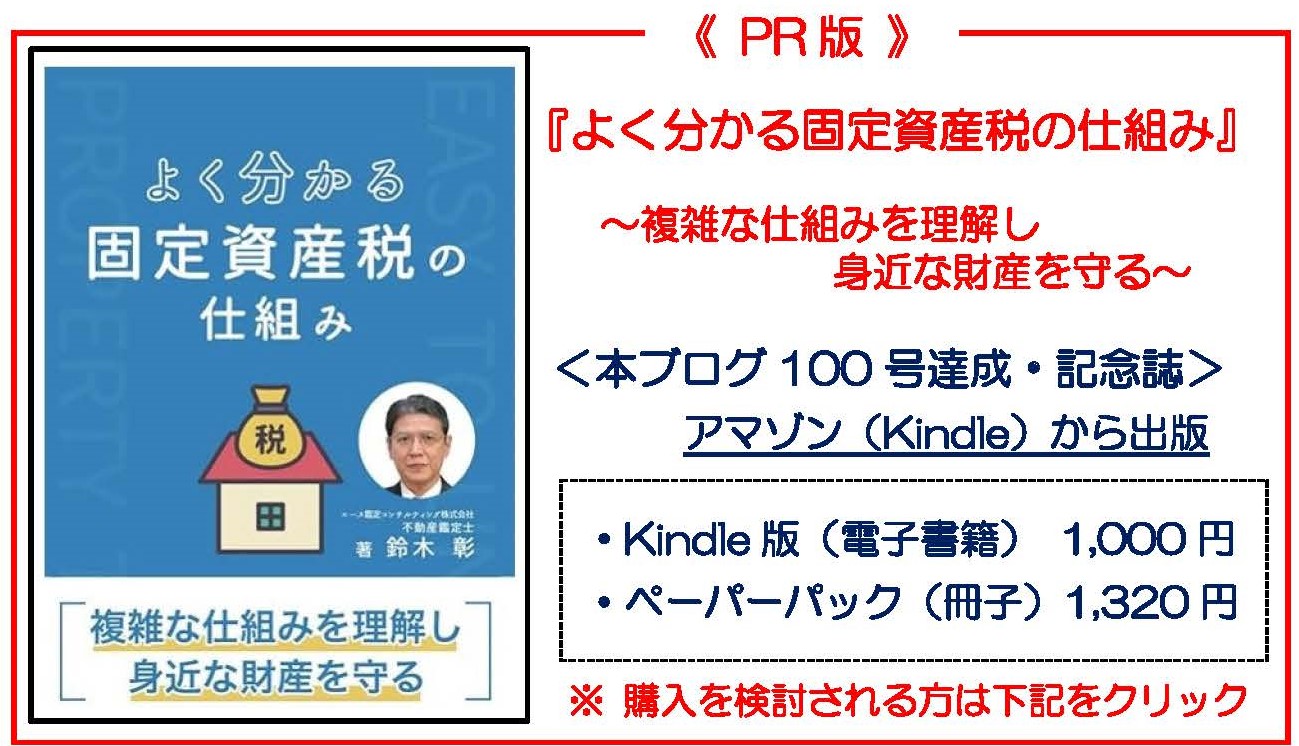
(投稿・令和4年9月-見直し・令和7年3月)
今回は、固定資産税の土地と家屋の価格に不服がある場合の、「審査の申出」の手続き及び流れについて説明します。
これまでも、価格に不服がある場合の手続きについては(部分的ですが)説明してきました。
第60号では、価格に不服があるからとしても、安易に「審査の申出」を行うのではなく、まずは課税庁に評価内容を問い合わせて、納得できるかどうかを確認すること。そして、その過程の中で「課税誤り」も見つかることがあることも説明してきました。
しかし、「審査の申出」は、地方税法上で「審査申出前置主義」として、訴訟を提起する前提の原則的手続きとなっていますので、この内容は理解しておかなければなりません。
そこで今号では、今まで触れてこなかった部分について解説することとします。
固定資産評価審査委員会とは
固定資産税の「審査の申出」は、納税者で固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3ヵ月以内に、文書をもって固定資産評価審査委員会(以下「審査委員会」)に「審査の申出」をすることができます。(地方税法432条1項)
<固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申出>
「地方税法第432条1項」
「固定資産税の納税者は、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合においては、第411条第2項の規定による公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日までの間において、文書をもつて、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる。(中略)」
固定資産評価審査委員会の設置
固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するために、市町村に審査委員会を設置することとされています。
<固定資産評価審査委員会の設置、選任等>
「地方税法第423条1項」
「固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するために、市町村に、固定資産評価審査委員会を設置する。」
そこで、なぜ審査委員会の制度が採用されているかですが、平成2年の最高裁(小法廷)判決では、次の説明があります。
<最高裁小法廷判決(平成2年1月18日)>
「法が固定資産登録価格についての不服の審査を評価、課税の主体である市町村長から独立した第三者機関である委員会に行わせることとしているのは、中立の立場にある委員会に固定資産の評価額の適否に関する審査を行わせ、これによって固定資産の評価の客観的合理性を担保し、納税者の権利を保護するとともに、固定資産税の適正な賦課を期そうとするものであり…」
審査委員の定数及び選任
審査委員会の委員の定数は3人以上ですが、具体的には市町村の条例で定めることとされています。
<審査委員会の委員の定数>
「地方税法第423条2項」
「固定資産評価審査委員会の委員の定数は3人以上とし、当該市町村の条例で定める。」
そこで、主な大都市の条例(施行規則)を調べてみますと、「定数は○名(以内)」と様々な人数となっていますが、審査(審査委員会)は3人の合議体で行われています。
合議体は事案ごとに構成され、審査委員会が指定する者1人が審査長となり、議事は合議体を構成する委員の過半数(2人以上)をもって決定されます。
<審査委員会の委員の選任>
「地方税法第423条3項」
「固定資産評価審査委員会の委員は、当該市町村の住民、市町村税の納税義務がある者又は固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、当該市町村の議会の同意を得て、市町村長が選任する。」
この「市町村税の納税義務がある者」ですが、その市町村に納税義務を負う者であれば、税目は固定資産税には限られません。
「審査の申出」ができる者
「審査の申出」が出来る者(審査申出人)は、固定資産税の納税者(課税年度の賦課期日である1月1日現在の固定資産の所有者)で、固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある者です。
ただし、次の事項に注意する必要があります。
(1) 借地人や借家人等の利害関係人は審査申出人となることはできません。
(2) 納税管理人も代理人でないかぎりは審査申出人とはなりません。
(3) 固定資産を共有している場合、共有者は単独で審査申出をすることができます。
(4) 区分所有家屋の場合、各区分所有者は単独で「審査の申出」をすることができます。
(5) 「審査の申出」は代理人によってもすることができます。ここでの代理人は、弁護士、税理士、公認会計士等には限られてはいません。
審査申出の流れ
審査申出書の形式審査
審査申出書が提出されると、不服の内容を審査する前に、まず必要な添付書類があるか、期間内に提出されたものであるかなど、適法な形式を備えているかが審査されます。
例えば、審査申出期間後に提出された審査申出書等は不適法となるため、却下となります。
合議体による1回目の審査委員会を開催し、審査の申出の内容が適法であるか審査し、受理または却下を決定します。却下となった場合、内容の審査は行われません。
「審査の申出」の実質審査
(1) 審査委員会は審査申出書を受理したら、審査申出書の副本を評価庁(評価・課税部局)に送付します。
(2) 審査委員会は評価庁へ「弁明書」の提出を求めます。そして提出された「弁明書」の副本を審査申出人へ送付します。
(3) 審査申出人は反論がある場合、「反論書」を審査委員会へ提出します。
(4) 審査申出人は、希望をすれば審査委員会に対して、口頭で意見を述べることができます(「口頭意見陳述」)。
(5) また、審査委員会は、必要に応じて、実地調査等を行います。
「審査の申出」の審査決定
審査委員会は、弁明書、反論書、実地調査、口頭意見陳述などを経て、審査の申出にかかる事案の適正な価格(評価額)の適否を判断します。
そして、審査決定には「却下」、「棄却」、「認容」の3種類があります。
「却下」(審査の不受理)
内容の審査に入らず不受理となるものです。受理後審査途中であっても、価格(評価額)の修正があり、審査の申出目的の一部又は全部が消滅したときは不適法となり、一部又は全部却下となります。
「棄却」(主張を退ける)
審査申出人の主張は、価格(評価額)を修正すべき正当な理由にはあたらないとして、主張を退けることです。
「認容」(主張を認める)
審査申出人の主張の一部または全部を認め、価格(評価額)を修正することです。
審査委員会は審査決定のあった日から10日以内に審査申出人及び評価庁に決定書を通知します。
「審査の申出」決定までの期間
審査委員会が「審査の申出」を受けて審理をし決定するまでの期間がどのくらいかかるかは、事案毎に内容が異なるため一概には言えません。
ただし、上記で説明したとおり、審査は形式審査のみならず実質審査や現地調査も行うこととなると、それなりの期間を要することになります。
いくつかの市町村のホームページを見ると、次のようなコメントが掲載されています。
『委員会では、できるだけ早期に審査の決定を行うよう審理手続を進めますが、審理手続には慎重を期する必要があり、決定までに時間がかかることがありますのでご了承ください。』
ところが、地方税法では「申出を受けた日から30日以内に審査の決定をしなければならない」と規定されています。また、「30日以内の決定がないときは、却下の決定があったとみなされます」。そうしますと、審査申出人にもよりますが、その「却下決定」に不服があるとして、取消訴訟を提起することも出来る訳です。
この地方税法の趣旨は、「速やかに納税者の不服を処理すること」にありますが、実務的には30日以内に決定が可能となるケースは「審査を経た却下」程度で、実質審査を経る審査は数ヶ月(以上)はかかるのが通常です。
2022/09/28/21:00